1 遺言書がある場合と、遺言書がない場合の違い
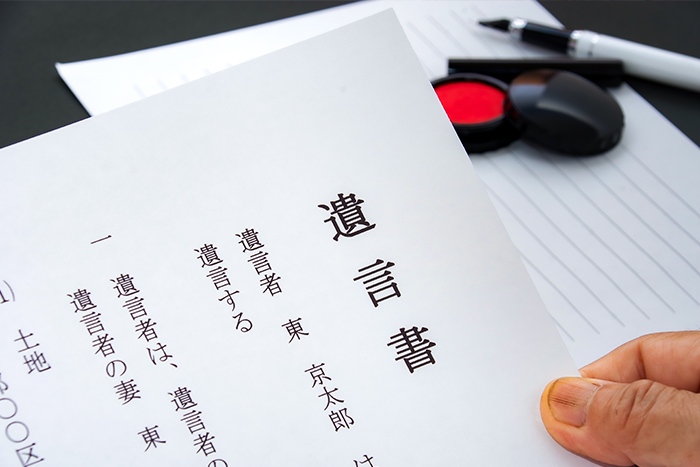
遺言書は、自分が将来、死亡した際に、自分の財産(=遺産)をどのようにしたいかについて、自分の意思を書き残す文書のことです。
法律の要件を満たした有効な遺言書には、法的な効力が認められることになっています。
遺言書がある場合と、遺言書がない場合の違いは、ひと言で言えば、法定相続人による遺産分割協議が必要となるか否か、です。
遺言書がない場合、すべての法定相続人が加わった遺産分割協議によらなければ、遺産分割をすることはできません。これに対して、遺言書がある場合は、原則として遺言書に記載された内容どおりに遺産分割を行うことになるため、必ずしも遺産分割協議は必要ありません。
このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、遺産分割の基本的な方法が異なります。
▼遺言書がない場合の遺産分割の方法と流れ▼

2 遺言書がある場合の遺産分割の流れ
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。公正証書遺言は公証役場で作成されるもので、自筆証書遺言は本人が手書きで作成するものです。それぞれの場合について説明します。
(1)自筆証書遺言がある場合
自筆証書遺言がある場合、まずは家庭裁判所での検認手続が必要となります。検認手続とは、遺言書の内容を確認する手続です。この検認手続を経ていなければ、自筆証書遺言に基づいて預金を解約したり、不動産の所有名義を変更するといった手続きをすることはできません。
もっとも、検認された遺言書であっても、それに従った遺産分割がなされない場合があります。たとえば、遺言書に記載された内容の意味が不明確な場合などです。その場合、遺言書に記載された内容をどのように解釈するか等を含めて、法定相続人間で協議することになるので、結局、遺産分割協議が必要となります。
また、検認手続を経たとしても、それにより自筆証書遺言が法的に有効なものであると確定するわけではありません。
たとえば、「自筆証書遺言が偽造である」とか、「自筆証書遺言の作成日付の時点で既に認知症が悪化していて判断能力がなかったはずだ」とか、自筆証書遺言の有効性を争う人が出てきた場合、有効か無効かは、別途、訴訟手続で判断されることになります。
(2)公正証書遺言がある場合
公正証書遺言がある場合、家庭裁判所での検認手続は必要ありません。検認手続を経ることなく、公正証書遺言のみに基づいて預金を解約したり、不動産の所有名義を変更するといった手続きをすることができます。
公正証書遺言の作成には、必ず、公証人が関与します。公証人は、元裁判官や元検察官といった法律家です。ですので、本人が作成する自筆証書遺言とは異なり、基本的には、形式的な法律要件を備えていますし、記載内容も明確です。
(3)遺言執行者の定めがある場合
自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの場合でも遺言執行者の定めがない場合には、遺言書に記載された内容を実現するためには法定相続人が動かなければいけません。したがって、その際に法定相続人による話し合いが必要になってきます。
他方、自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの場合でも遺言執行者の定めがある場合には、その遺言執行者が遺言書に記載された内容を実現するために動きます。遺言執行者は法定相続人の協力を得ずとも単独で遺言の内容を実現できる地位にあるので、この場合は法定相続人による話し合いは必要ありません。






